Keeley Manis Overdriveを見たとき、メーカーとしては珍しい印象。Keeleyといえばコンプレッサーやモダンなディレイ/リバーブ系のイメージが強かったので、まさかトランスペアレント系のオーバードライブを出すとは思っていなかったんです。しかもベースはKlon系。モダンなメーカーが「伝統のKlonサウンド」にどう挑んだのか、試さずにはいられませんでした。
Keeleyとはどんなメーカーか
アメリカ発のKeeley Electronicsは、いわゆる「モダン系」エフェクターブランド。独自設計の空間系やコンプレッサーで名を広めましたが、近年はクラシックな名機をアップデートする「Keeley流のオーバードライブ開発」にも力を入れています。特徴的なのは「ただ回路をコピーするのではなく、必ず+αの解釈を加えて現代的な使い勝手に仕上げる」点。今回のManisもまさにその姿勢が表れているペダルです。
Keeley Manis Overdrive:機能・特徴

一言でいえば「Klonを基盤にしたモダンアレンジ」。コントロールはLevel、Tone、Driveとシンプルですが、そこに2つの大きな特徴が加わります。
- クリッピング方式を切り替え可能
- Germanium Diode:伝統的なKlonサウンド。中域が前に出てミックスで埋もれない。
- Germanium Transistor:より柔らかく、真空管アンプのようなコンプレッション感と倍音。
- Bass Boostスイッチ
低域を補強し、シングルコイルを太くしたり、ハムバッカーにさらに力強さを加えることが可能。
さらに、18V駆動による広いヘッドルーム、True / Buffered Bypassの切替など、細かい部分にも気が配られています。
Keeley Manis Overdrive:クリッピング方式を切り替えについて
Keeley Manis Overdrive の最大の特徴のひとつが、クリッピング方式をスイッチひとつで切り替えられる点です。通常、オーバードライブペダルは内部で信号を「どのように歪ませるか」が固定されており、回路の設計によって音のキャラクターが決まります。しかしこのペダルは、GermaniumダイオードとGermaniumトランジスターという2種類の異なるクリッピング素子を自由に選べる設計になっています。
- Germaniumダイオード
伝統的なKlonスタイル。中域がグッと前に出て、ミックスの中で抜ける音になります。アタックが強く、ロック的な「ガツン」としたサウンドを作るのに最適。 - Germaniumトランジスター
Keeley独自の新しいアプローチ。より低い電圧で滑らかにクリッピングし、真空管アンプのようなコンプレッション感とサステインを生み出します。音が柔らかく太くなるので、ソロやバラードで「歌う」ようなトーンを作りたい時に有効です。
つまりこの切り替えは、1台で2種類の性格の異なるオーバードライブを使えるということ。曲ごとにキャラクターを変えたり、ギターの種類に合わせて最適な歪み方を選んだりできる柔軟性を持っています。
Keeley Manis Overdrive:2色のラインナップ

Keeley Manis Overdrive は、標準的なシルバー筐体に加え、ブラックのバリエーションも用意されています。どちらも性能や回路はまったく同じですが、見た目の印象が大きく異なるため、ペダルボードの雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。
Keeley Manis Overdrive:実際の使用感

1. クリッピング方式の切り替えが新鮮
本機最大の特徴は、ゲルマニウム・ダイオードとゲルマニウム・トランジスターの切り替え。
プレイスタイルや曲調に応じて切り替えられるのは本当に便利で、2台分のペダルを1台に収めたような安心感があります。
2. Bass Boost が単なるおまけではない
低域を1オクターブ下で押し出す Bass Boost スイッチが秀逸。シングルコイルのテレキャスターやストラトでは、これをオンにするだけでソロ時に太さが増し、バンドサウンドに負けません。リズムでオフ、ソロでオンと使い分けると非常に効果的でした。
3. ヘッドルームの広さ
18V駆動に対応しているため、ブースト幅やクリーン感の余裕が大きいです。小音量でも音が潰れず、ライブ会場の大音量でも暴れすぎないコントロール性を持っています。特にフェンダー系のクリーンアンプに合わせると、その違いは顕著でした。
4. 細やかな設計思想
トゥルーバイパスとバッファードバイパスを切り替え可能、静音スイッチング対応など、ステージでもレコーディングでも気が利いています。小ぶりな筐体にこれだけの機能を詰め込んでいるのは、Keeleyらしい実用性重視の設計です。
Keeley Manis Overdrive:気になったポイント
1. クローン的“魔法感”はやや控えめ
確かにクローンの中域の押し出しや透明感は再現されていますが、オリジナルの神秘的な「音が前に出る魔法感」と比べると少し整いすぎている印象があります。良くも悪くも“現代的な完成度”といった感じです。
2. 音量差の扱いに注意
トランジスターとダイオードを切り替えたとき、わずかに出力感が変わります。特にトランジスターモードは音量が下がったように感じるため、ライブ中に切り替える場合はレベル調整を詰めておかないと戸惑うかもしれません。
3. 値段の高さ
3万5千円という価格は、同じくクローン系ペダル市場に並ぶモデルと比べてもやや高め。2つのキャラクターを搭載していることを考えれば妥当ですが、「クローン系を試したい初心者」には手を出しにくい価格帯かもしれません。
Keeley Manis Overdrive:他のペダルとの比較
やはり気になるのは、Klon系や他のトランスペアレント系との違いです。
- Klon / KTR系との違い
→ Manisは「Klonらしさ」をしっかり再現しつつ、Transistorモードでよりモダンなサウンドを提案しているのがポイント。クラシックかモダンかを1台で選べるのは大きな強み。 - Xotic EP BoosterやRC Boosterとの違い
→ EP Boosterが「艶」を、RC Boosterが「フラットなブースト」を得意とするのに対し、Manisは「歪みの質感」を切り替えてキャラクターごと変えられる。
この違いによって、ただのクローンではなく「Klonを踏み台にしたKeeleyの答え」と言える存在になっています。
Keeley Manis Overdrive:Q&A
Q. 電源はどうすればいい?9Vでも動く?
A. Manis は 18V駆動推奨です。9Vでも動作しますが、本来の広いヘッドルームや余裕あるダイナミクスを引き出すには18Vを使った方がベター。特にクリーンブースト的に使いたい場合は、18V駆動が大きな差になります。
Q. 18V駆動だとアダプターを別に買う必要がある?
A. 多くの標準的なパワーサプライは9V出力が基本なので、18Vで使いたい場合は「電圧倍加ケーブル」や18V出力可能なパワーサプライが必要です。音の余裕感に直結する部分なので、ここは投資する価値があります。
Q. ペダルボードのどこに置くのがいい?
A. 使い方次第で変わります。
- 常時オンのプリアンプ/トーンシェイパーとして使うなら、最前段。
- ブースター用途なら歪みペダルの前。
- 音量アップやソロ用なら歪みペダルの後段。
モードやセッティングによってキャラクターが大きく変わるので、自分のメイン歪みとの相性を確認して最適な位置を見つけるのがおすすめです。
Q. ジャンル的にはどこに向いてる?
A.
- ブルース/ロックではクランチ〜ミディアムゲインが心地よく、特にシングルコイルのギターと好相性。
- ポップス/ファンクではクリーンブーストやトランジスターモードの滑らかな歪みで、コードワークが生きる。
- ハードロック/モダンロックでも、ブースターとして使えばハイゲインアンプをしっかり押し出してくれる。
つまり「万能だけどキャラを選べる」タイプで、特定のジャンルに縛られないのが強みです。
Q. 他のエフェクターと比べてノイズはどう?
A. 18V駆動&Keeleyらしい高い作り込みで、ノイズはかなり少ないです。ただしゲインを高めに設定するとハムノイズは拾いやすくなるので、シングルコイルのギターを使う場合は気をつけた方がよいでしょう。
Q. 長時間使ったときの感覚は?
A. トランジスターモードは耳に優しく、長時間弾いても聴き疲れしにくい印象。一方、ダイオードモードはミッドが前に出る分、バンドアンサンブルの中で存在感を出したいときに重宝します。演奏シチュエーションでモードを使い分けるのが効果的です。
Keeley Manis Overdrive:まとめ こんな人におすすめ

Keeley Manis Overdriveは、Klonをそのままコピーするのではなく、「伝統を踏まえつつ新しいサウンドの選択肢を提示する」ペダルでした。
- クラシックなKlonサウンドを欲しい人
- もう一歩モダンな質感を求める人
- ギターやアンプの個性を活かしながら音を前に出したい人
この3つの層に強くおすすめできる1台です。
「Klonクローンのさらに先」を提示してくれる、Keeleyらしい答えがここにありました。
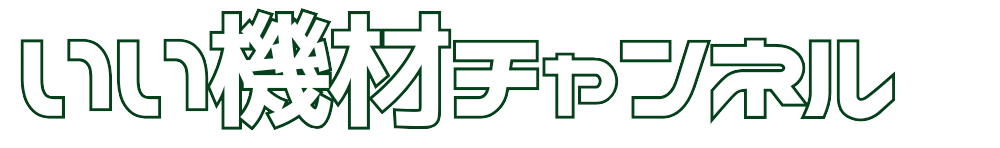




コメント