今回紹介するのは MXR CSP027 Timmy Overdrive。
このペダルは、トランスペアレント系オーバードライブの代名詞とも言われるPaul CochraneのTimmyを、MXRがコラボレーションして再現したモデルです。
オリジナルのTimmyはすでに生産されておらず、中古市場では6〜8万円ほどの値が付いています。そんな名機を、MXRが手頃な価格で、しかもコンパクトな筐体に収めて再登場させたのです。新品価格は3万円前後。MXRブランドという安心感もあり、気になる存在でした。
MXR Timmy Overdrive:デザインと操作系
見た目はMXRらしい青い筐体。小型ながらしっかりとした作りで、エフェクトボードに組み込みやすいサイズ感です。
コントロールは以下のとおり:
- VOLUME … 出力レベル調整。クリーンブースター的な使い方も可能。
- GAIN … 歪み量をコントロール。
- BASS … オーバードライブ回路の前段で低域をカット。Timmy独自の設計。
- TREBLE … 後段で高域を調整。
- CLIP … 3種類のクリッピングを切り替え可能。
特徴的なのはEQの効き方です。BASSとTREBLEはブーストではなくカット方向で動作するため、基本の音を削るイメージ。これが「原音を活かす透明感」に繋がっています。
MXR Timmy Overdrive:サウンドの特徴

出典:モリダイラ楽器
まず驚いたのは、クリーンブーストとしての美しさ。GAINを絞り、VOLUMEを上げるとギター本来の音色を際立たせてくれるようなクリアさがあります。
GAINを上げると、クランチから軽いオーバードライブまで対応。Stratではキラッとした抜け、Teleではアタック感のあるカッティング、Les Paulでは太く伸びのあるリードトーンが得られました。ギターごとのキャラクターを邪魔せずにプッシュしてくれる感覚です。
CLIPスイッチを切り替えると、コンプレッションのかかり具合やニュアンスが変化。オープンな真ん中ポジションは抜けが良く、左右に切り替えると少しマイルドまたはコンプ感強めのサウンドになります。極端に変わるわけではなく、ニュアンスの差を選べるのがポイント。
MXR Timmy Overdrive:オリジナルとの違い

Paul CochraneによるオリジナルTimmyは、レンジの広さと抜群の分離感が最大の特徴です。クリーンからクランチまで、ギター本来の音色を損なわずにそのまま前に押し出してくれる印象があり、まさに「トランスペアレント系」と呼ばれる所以がここにあります。ローからハイまでのレンジがしっかり出て、各弦の粒立ちも明瞭。プレイヤーのニュアンスがそのまま反映されるため、表現力を重視する人にとって理想的なペダルです。
一方で、MXR版Timmyはサイズがコンパクトになっただけでなく、全体的にコンプレッションが効いたまとまりのあるサウンドへと調整されています。その結果、原音を忠実に再現するという点ではオリジナルより一歩引きますが、逆に「扱いやすさ」という意味では大きな強みになります。分離感の鋭さはやや抑えられているものの、ライブや録音の現場では音が暴れにくく、安心して使える印象です。
さらにMXR版では、EQの効き方が通常のペダルと同じ方向に設計され直している点もポイントです。本家は「カット方向だけで調整する」という独特な仕様でしたが、MXR版は直感的に扱えるようになっており、初めて触る人でも迷いにくいでしょう。またクリッピング切り替えによって、軽いコンプレッションからより強いコンプレッションまで選べるため、好みに合わせて音作りできる柔軟さも持ち合わせています。
MXR Timmy Overdrive:実際に使ってみて
ライブやスタジオで試して感じたのは、細かな調整がシビアだという点。ノブが小さく、少し触るだけで音の印象が変わるので、事前に自分の“ベストポジション”を見つけておくことが大切です。
録音では特に力を発揮します。低域を削ることでベースやドラムと被らず、クランチ系のギターが綺麗にミックスに収まります。クリーン寄りに使えば極上のブースター、歪みを足せば心地よいオーバードライブ。まさに万能型の1台です。
MXR Timmy Overdrive:使って分かった良い点、気になった点
良かった点
MXR Timmy Overdriveの魅力は、まずそのトランスペアレント系らしい原音重視のサウンドにあります。ギター本来のトーンを損なわず、あくまで自然なドライブを付与してくれるため、ピッキングのニュアンスやギターごとのキャラクターをそのまま活かすことができます。クリーンブースト的な使い方から、軽く歪ませてクランチを得るところまで幅広く対応でき、プレイヤーの演奏スタイルに柔軟に寄り添ってくれるのは大きなメリットです。また筐体が非常に小型で、エフェクターボードに組み込みやすいのも実用的。オリジナルのTimmyは中古市場でも高額で取引されることが多いですが、MXR版は2万円台と比較的手に届きやすい価格設定となっており、入手性の高さも魅力のひとつでしょう。
気になった点
一方で、気になる点も存在します。まず、筐体が小型であることの裏返しとしてノブが小さく、ライブ中に素早くセッティングを変えるのは難しいと感じる場面があります。また、オリジナルのTimmyと比べると、音のレンジ感や分離感の面でやや劣る印象を受けるという声もあります。特に粒立ちの明瞭さを重視する人にとっては、本家の持つ抜けの良さと比較して違いを感じるかもしれません。そして、全体として低〜中ゲインを得意とする設計であるため、ハイゲイン用途での使用には不向きです。しっかり歪ませたいプレイヤーには物足りなさが残るでしょう。
総じて、このペダルは「ギター本来の音を活かしながら軽くプッシュしてあげたい」場面に最も輝くタイプだといえます。
MXR Timmy Overdrive:Q&A
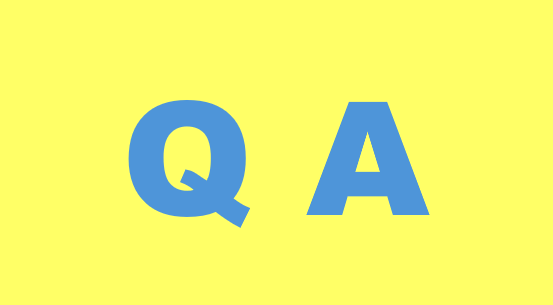
Q1. 本家Timmyとの違いは何ですか?
A1. Paul CochraneによるオリジナルTimmyはレンジが広く、非常に透明感のあるサウンドが特徴です。一方、MXR版はコンパクト筐体化に伴い若干コンプレッション感が加わり、音がまとまりやすく扱いやすい設計になっています。そのためライブやレコーディングでの実用性を重視する方にはMXR版が便利です。
Q2. EQの効き方が特殊と聞きましたが?
A2. TimmyのEQは「カット専用」で、BASSはオーバードライブ前、TREBLEはオーバードライブ後に位置しています。ゼロ位置がフル帯域で、そこから不要な帯域を削っていく仕組みです。通常のトーンノブとは逆の考え方になるため、最初は戸惑うかもしれませんが、ミックスに馴染ませやすいメリットがあります。
Q3. クリーンブースターとしても使えますか?
A3. はい。GAINを絞り、VOLUMEを上げると極上のクリーンブーストとして機能します。原音を損なわずに音量を押し出したいときや、アンプのナチュラルドライブを活かしたいときに最適です。
Q4. クリッピングスイッチはどう使うのでしょうか?
A4. 3種類のクリッピングを切り替えることで、コンプレッション感や音の抜け具合が変化します。真ん中のポジションはもっともオープンで抜けの良いトーン、左右に倒すとコンプレッションが強まり、まとまったサウンドになります。演奏スタイルや楽曲に応じて選択すると効果的です。
Q5. 電池は使えますか?
A5. 残念ながら電池駆動には対応していません。必ず9Vアダプターを使用する必要があります。
Q6. バイパス方式は?
A6. True Hardwire(トゥルー・バイパス)方式を採用しています。エフェクトをオフにした際には音声信号が回路を通らず、そのまま出力されるため、音痩せや余計な色付けを避けられます。
Q7. どんなジャンルに向いていますか?
A7. トランスペアレント系の特性から、ジャンルを問わず幅広く対応できます。特に、ブルースやカントリー、ポップスなど原音のキャラクターを活かしたいジャンルで活躍します。ゲイン幅は広いので、軽いロックのドライブサウンドも十分カバー可能です。
MXR Timmy Overdrive:まとめ

出典:モリダイラ楽器
MXR Timmy Overdriveは、オリジナルTimmyの血統を受け継ぎつつ、現場での実用性と扱いやすさを高めたモデルといえます。Paul Cochraneによる本家のTimmyは、レンジの広さと抜群の透明感、そして弦の粒立ちをそのまま活かせる表現力が大きな魅力です。一方で、MXR版はコンプレッション感が加わったことで音がまとまりやすく、初めてトランスペアレント系に触れる人でも使いやすいチューニングになっています。
EQの効き方も直感的に扱えるよう改良され、3種類のクリッピング切り替えにより音のキャラクターを簡単に調整可能。クリーンブーストからクランチ、さらには軽いドライブまで幅広く対応できる汎用性を備えています。サイズがコンパクトでペダルボードに収めやすく、価格も2万円台前半と、本家と比べれば非常に手の届きやすい点も見逃せません。
結果としてこのペダルは、「Timmyの思想を体験したいが本家は手に入りにくい」「実用性を重視したコンパクトなトランスペアレント系が欲しい」というギタリストに強くおすすめできる1台です。オリジナルの持つ繊細さとは少し方向性が異なるものの、MXRらしい信頼感とコストパフォーマンスで、多くの場面で頼りになる相棒となるでしょう。
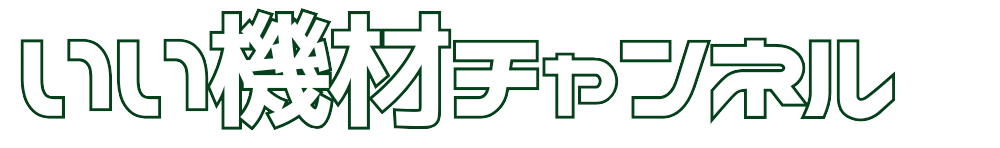




コメント