VEMURAMとは?Jan Rayの成り立ちとブランドの哲学

出典:vemuram
VEMURAM(ベムラム)は東京を拠点に世界中のプロ・ミュージシャンに愛されているエフェクターブランドであり、その高品質な回路設計と外装の美しさから“プレミアム・ペダル”として絶大な評価を受けています。
Jan Ray(ジャンレイ)はVEMURAMの代表作ともいえるオーバードライブペダルで、その開発コンセプトは「ヴィンテージのフェンダー・ブラックフェイスアンプのような響きを現代のペダルで再現する」ことにあります。開発者はTS系の回路をベースにしつつも、より広いレンジとナチュラルな歪み、優れたレスポンスを持つペダルを目指して作り上げたと言われています。
また、筐体にはブラス(真鍮)が使われており、ノイズ耐性に優れ、ペダル全体の高級感を引き立てています。このこだわりが、プロギタリストからの圧倒的な支持に繋がっています。アメリカのDoyle BramhallやJoey Landrethといった著名なプレイヤーも使用しており、その信頼性は折り紙付きです。
サウンドキャラクター
「真空管のようなコンプレッション」と「倍音の豊かさ」Jan Rayのサウンドを一言で表すなら、「自然で艶やか、そしてレンジが広い」。ローゲインオーバードライブとして知られるこのペダルは、クリーン〜クランチ程度の歪み領域を中心にしつつ、しっかりとドライブさせることもできます。
最大の特徴は、真空管アンプに似たコンプレッション感と、弾いた瞬間に音が前に出てくるようなレスポンス。音の立ち上がりが非常に滑らかで、強く弾けば歪み、弱く弾けばクリーンなトーンに戻る——その挙動はまさに“楽器の一部”として扱える感覚です。
ピッキングのニュアンスに対する追従性も抜群で、細かな表現の違いをしっかりと出してくれます。コードプレイ時にも音の分離感が高く、ローコードでも濁らず一音一音がしっかり聞こえる仕上がりになっています。
また、特筆すべきはトーンの帯域設計。ローはしっかりと出ますが、ブーミーにはならず、ローミッドが中心となって腰のあるサウンドを構成しています。ハイは耳に痛くない程度に抜けてきて、アンサンブルの中でも埋もれない存在感を放ちます。
コントロール部の構成とセッティングの柔軟性

出典:vemuram
Jan Rayは4つのノブで構成されています。
Volume:全体の出力音量を調整。
Gain:歪み量のコントロール。
Bass:低域の調整。
Treble:高域の調整。
これに加えて、内部にあるトリムポット(サチュレーショントリマー)を調整することで、倍音の量や歪みの質感を微調整できます。これがまた絶妙で、音を“ギラつかせる”方向にも、“マイルドにする”方向にも振れるため、非常に幅広いキャラクター作りが可能。

多くのレビューでは、「アンプのEQを操作するような自然さ」と表現されており、実際にどのノブも極端な効き方はせず、あくまで音楽的な範囲で効いてくれます。
特に面白いのが、VolumeとGainのバランスによってクリーンブースターとしても、ミドルゲインオーバードライブとしても成立する点。ギター本体のボリュームとの連携も良好で、「常時ON」にしてプリアンプ的に使うユーザーも多く見られました。
実勢価格とその価値

Jan Rayの新品価格は約46,970円(税込) ※2025年4月時点
エフェクターとしては高価な部類に入るのは間違いありませんが、「この1台で全てが変わった」「他の安価なオーバードライブを買い漁るより、これを1台持つ方が早い」と語るギタリストも少なくありません。
中古市場でも流通量は多く、4万円前後でのやり取りが主流。万が一手放すことになっても比較的高値で売却しやすく、リセールバリューも非常に高い点は見逃せません。
言い換えれば「一度試して気に入らなくても、ほぼ定価に近い金額で売却可能」という安心感もあり、購入のハードルは思っているよりも低いかもしれません。
使用感から見えたメリット・デメリット
VEMURAM Jan Rayを実際に使ってみてまず驚くのは、ペダルをオンにした瞬間の音の変化です。クリーンな状態からONにするだけで、輪郭のある艶やかでリッチなサウンドに変化し、「あ、これがプロの音か」と直感的に思えるような“整った”音に仕上がります。しかもそれが、ギターやアンプの個性を押し殺さずに実現されるのだから驚きです。
この“完成されたサウンド”は、ギタリストにとって大きなメリットです。倍音の美しさ、適度なコンプレッション、絶妙なローの粘りとハイの抜け感は、まさに高級真空管アンプを通したようなフィーリングに直結します。どのセッティングでも「良い音になる」という安心感があり、特にシングルコイルのギターではその効果が如実に現れます。ストラトやテレキャスの輪郭がより引き立ち、繊細でありながら芯のあるトーンが得られます。
また、ペダルの設計自体も非常に優れており、ノブやスイッチの操作感、エンクロージャーの堅牢性も抜群。電源ジャックの位置ひとつ取っても、ボードへの収まりやすさが計算されています。ライブやレコーディングの現場で長く使える、プロスペックな設計がなされています。
一方、デメリットとしてまず挙げられるのは「価格の高さ」です。新品で4万円を超える価格帯は、決して気軽に試せるものではありません。とはいえ、これ1台で得られるサウンドクオリティや汎用性を考えると、長期的に見てコストパフォーマンスは非常に高いとも言えます。
もうひとつの弱点は“キャラクターの整いすぎ”です。Jan Rayは非常にバランスよく仕上げられているがゆえに、荒々しさや予測不能な暴れ感、クセの強さといった要素はあまり感じられません。ある種の“優等生”であり、ロックやガレージ系などで「もっと汚したい」と感じるプレイヤーにとっては、少々物足りないかもしれません。
また、ハイゲインには不向きで、メタルやモダンなハードロックサウンドを求めるプレイヤーには用途が限られます。あくまでロー〜ミドルゲイン領域で、タッチレスポンスや倍音、艶のあるサウンドを求める人に最適化された設計です。
それでも、機材を“弾き手の音楽性を引き出す道具”と捉えたとき、Jan Rayはその理想に限りなく近いペダルです。「繋ぐだけで音が完成する」と感じられるほどの精度と美しさ。だからこそ、プロアマ問わず多くのギタリストに愛され、ボードの常連となっているのでしょう。
Q&A

Q1. アンプの種類によって相性はありますか?
A. Jan Rayはアンプのキャラクターを尊重するタイプのペダルなので、基本的にはどんなアンプとも相性が良いです。特にフェンダー系、マッチレス、トゥーロックなどのクリーン寄りアンプとの組み合わせが秀逸とされており、ブラックフェイスアンプの“理想の歪み”を再現する目的でも人気があります。ただし、すでに歪みの強いアンプでは効果が薄く感じる場合もあるため、クリーン〜クランチ系アンプとの併用がオススメです。
Q2. 他のVEMURAM製品との違いは?
A. Jan RayはVEMURAMの中でも最もスタンダードで多用途なモデルです。より歪みに特化したペダル(Shanks ODやKarenなど)とは違い、トーン補正、プリアンプ的使用、軽い歪みの追加など、幅広い役割を担えるのが特長です。初めてVEMURAMを試すなら、まずはJan Rayから入るのがオススメです。
Q3. Jan Rayは電池で駆動できますか?
A. はい、9V電池での駆動が可能です。小型の筐体ながら、内部に電池を収めるスペースがしっかり設計されており、ライブや外出先などでアダプターを使えない場面でも安心して使用できます。ただし、ペダルを長時間使用する場合や、電池残量によって音質が微妙に変化することもあるため、安定した音質を求めるならアダプターでの運用がオススメです。また、電源ジャックは筐体のサイドに配置されており、ボードへの組み込みや取り回しも良好です。
Q4: Jan Rayは18Vで使用できますか?
A: Vemuramの公式情報によれば、Jan Rayを含む同社のペダルは18Vでも動作します。ただし、元々9Vでの使用を前提に設計されているため、18Vでの使用は推奨されていません。高電圧での使用による損傷については責任を負いかねるとのことです。
Q5: Jan Rayはトゥルーバイパスですか?
A: はい、Jan Rayはトゥルーバイパス設計となっています。これにより、エフェクトオフ時には信号が直接アンプに送られ、音質の劣化を防ぎます。
Q6: Jan Rayの内部トリムポットを調整する際の注意点はありますか?
A: 内部トリムポットを調整する際は、必ず電源をオフにし、慎重に行ってください。過度な調整はペダルの動作に影響を与える可能性があります。また、メーカーの推奨設定から大きく外れる調整は避けることが望ましいです。
まとめ
“弾いた瞬間に上質な音”を求めるなら、選ぶ価値あり。VEMURAM Jan Rayは、その価格に見合うだけのサウンドとレスポンス、そしてプロの現場でも十分に通用するクオリティを備えたオーバードライブペダルです。
どんなジャンルにも自然に馴染むサウンドと、音楽的に優れたコントロール性能。シングルコイル・ハムバッカー問わず美しく響き、ギターの個性をそのまま押し出してくれる表現力。
「弾いた瞬間に“良い音”を手に入れたい」——そんなプレイヤーにとって、これほど信頼できる1台はそう多くありません。
価格面でのハードルはあるものの、それを補って余りある説得力と音楽性。迷っているなら、まずは一度試してみる価値は大いにあると断言できます。

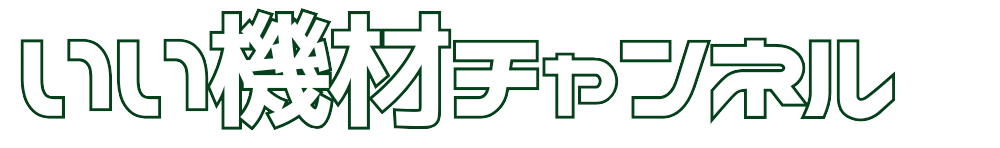




コメント